小山弘美 (関東学院大学社会学部教授)
かつては他の人が収集した「二次データ」よりも、自分で調査をして収集する「一次データ」が重要だという風潮があった。しかし、気軽に調査ができてしまう今日にあって、逆に二次データを分析する重要性が高まってきている。データサイエンスが注目され、何事もデータによるエビデンスが求められる状況のなかで、社会調査データはオープンに共有されるようになってきた。実際に調査を行う技術よりも、二次分析を行う技術が求められる社会と言えなくもない。

社会調査実習授業の様子1
ここで扱う二次分析は、自分(たち)ではない他の誰かが調査した統計調査の個票データを二次的に分析することを指す。例えば、東京大学社会科学研究所の社会調査・データアーカイブセンターには、民間の研究所や大学の研究者が行った調査データが実に2000件近くも収集されている。そして、研究や教育が目的であれば、データを申請して利用することが可能である。国や自治体が行う調査のデータも、申請するなどして使用できることも増えてきている。例えば 「横浜市市民意識調査」は、個票データがHP上で誰でもダウンロードできる。このデータを分析すれば、住民の特徴や意向を知ることができるのであり、社会調査を学んだみなさんは、これが可能だというわけだ。
データと向き合う―二次分析の手法
さて、私が担当する社会調査実習では、二次分析の手法を用いる場合も多い。2023年度には、世田谷区が実施した「地域生活とコミュニティに関する調査」のデータを借り受け、これを学生の視点から分析した。
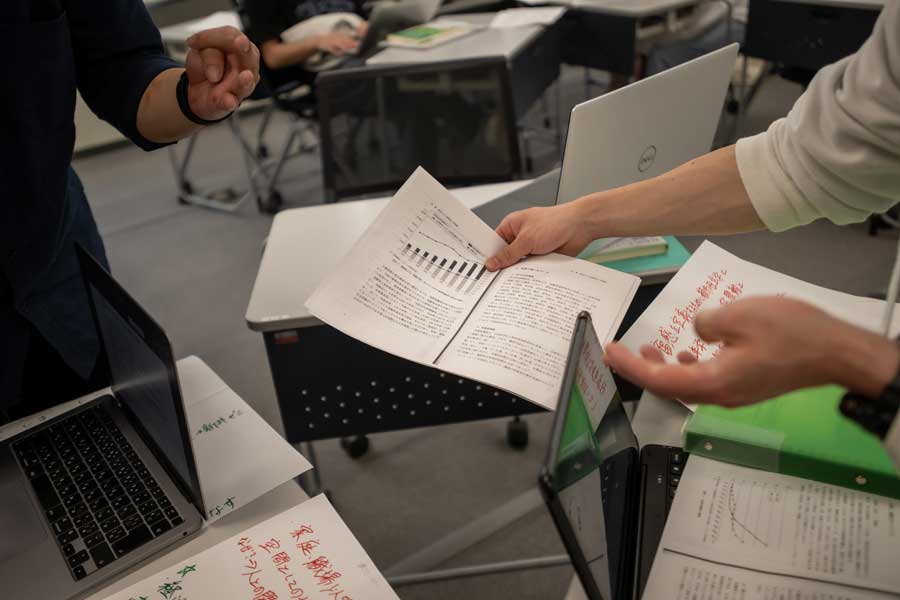
社会調査実習授業の様子2
自分たちで実査をしないものの、実際は調査過程の多くを体験していくことになる。まずは、仮説を構成するまでの事前調査が必要となる。関連文献を読み、調査対象地の特徴を知るために、フィールドワークを行い、行政職員から話を聞くことも行った。そのうえで、二次分析の対象となる調査の概要を確認し、調査票をじっくりと読み込む。単純集計や簡単なクロス集計結果から想像を膨らませて、自分なりの分析仮説を検討していく。
二次分析はすでに行われた調査であるため、自分の知りたい仮説に合った質問項目があるとは限らない。また当たり前だが、仮説通りに結果が出ないこともある。そこで、各質問項目の結果を足し合わせたり、いくつもの質問項目についてクロス集計や平均値を比較したり、気の遠くなりそうな作業が必要な場合もある。実際のデータで統計分析をすることは、座学で学ぶよりも苦労が多く、それは一次データでも二次データでも変わらない。しかしこうした作業の先に、自分だけの着眼点が反映された分析結果があり、発見がある。
多くの調査データがオープン化される潮流のなかで、苦労して調査実習で学んだ二次分析の手法を、今後もぜひ生かしてもらいたい。